
原付バイク50ccの時代終焉!!2025年4月からの原付バイクの新基準とは?
BLOG

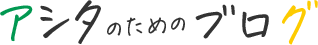
 その他
その他
「雇用保険」と聞いたとき、または、退職や転職をしようと考え始めたとき、まず思い浮かぶのが失業保険ではないでしょうか。
働きながら転職活動をするか、仕事を辞めてから転職活動をするか、悩む人は多いはず。
収入がない中、転職活動をするのはかなり不安ですが、そんなときに心強い制度が雇用保険制度の失業等給付「基本手当」。
今回は、失業保険とはどういう制度なのか、受けとれる条件や金額、申請方法について解説していきます!
退職や失業、転職をしようとした際に、多くの方はまず「失業保険をもらいたい!」と考えるのではないでしょうか。
失業保険は失業等給付制度に含まれる「基本手当」のことです。
失業保険という言葉が一般的に浸透していますが、実は失業保険という保険はないのです・・・!
ハローワークでは、基本手当について次のように明記しています。
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
引用元:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
基本手当は、再就職を促すために求職活動をするあいだも安定した生活ができるように・・・という意図で作られた制度のようですね!
そのため、基本手当を受給する場合は、なるべく早く再就職できるように積極的に求職活動を行いましょう!
基本手当の受給には、雇用保険に加入していることを前提として、2つの条件があります。
離職した場合でも、就職先が決まっている場合や家事に専念する場合、ケガや病気で療養中、妊娠・出産などで、すぐに仕事に就けないといった場合は給付を受けることができません。
会社都合で退職せざるを得なかった場合(特定受給者)や、自己都合でも正当な理由があった場合(特定理由離職者)については、その期間が1年間で通算6ヶ月以上と半減されます。
上記2つの受給要件を満たさない場合には、基本手当は受け取れません。
あくまでも、働きたいという意思がある方へ再就職への支援をするのが目的!ということがわかりますね!
基本手当を受給できる日数のことを「所定給付日数」と言います。
所定給付日数は90~330日のあいだで、離職した理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって日数は変わってきます。
雇用保険の被保険者であった期間が長期間の場合や、倒産・解雇などにより、再就職するための準備期間がないまま退職を余儀なくされた場合などは、一般の退職者に比べて所定給付日数が多くなります。
年齢に関わらず、雇用保険の加入期間で給付日数(支給期間)が決まります。

会社の倒産や事業所の廃止など、会社の都合により退職した場合は、「特定受給資格者」となります。
また、体力不足や病気、ケガにより離職した人、事業所の移転により通勤不可能または困難など、正当な理由による自己都合で退職した場合は、「特定理由離職者」となります。
これらの場合、被保険者であった期間と退職時の年齢で所定給付日数が決定します。

もっとも長い給付期間は330日ですが、これは離職時の年齢が45歳以上60歳未満で、雇用保険の加入期間が20年以上、なおかつ会社都合での退職となった場合に限定されていますね!
就職困難者とは、以下のような人などが該当します。
上記のような就職困難者の場合は、被保険者であった期間と退職時の年齢で所定給付日数が決定されます。

参考:よくあるご質問(雇用保険について)よくあるご質問(雇用保険について)Q4-A4|ハローワークインターネットサービス
給付金額の求め方は、以下の3ステップです!
賃金日額を求める ➤ 基本手当日額を求める ➤ 給付日数と基本手当日額から手当総額を求める
手当総額を計算するために、まずは賃金日額を求める必要があります。
賃金日額の求め方
❶ 離職前6ヶ月間の給料合計額を出す
❷ 給料合計額を参考に賃金日額を求める
失業保険の金額は、退職した会社から支払われていた給料の50~80%がもらえる決まりになっています。※60~64歳を除く
① 離職前6ヶ月間の給与合計を計算する
まずは、退職前6ヶ月間の給与額を調べます。
給与合計には退職金やボーナスは含めず、残業代・通勤手当などの各種手当は計算に含めるようにしましょう!
過去に支給された給与は、給与明細だけでなく退職時に受け取ることが可能な「離職票2」に記載されています。
② 給料合計額を参考に賃金日額を求める
過去の給与合計が出せたら、1日あたりの平均賃金を求めます。
①で求めた退職前6ヶ月間に支払われた給与合計 ÷ 180日(30日×6ヶ月)= 賃金日額
③ 離職時の年齢と賃金日額をもとに、基本手当日額を求める
②で求めた賃金日額を、離職時の年齢に基づいて計算していきます。
年齢によって給付率が変わり、以下の4パターンに分類されます。
離職時の年齢区分
❶ 29歳以下または65歳以上
❷ 30~44歳
❸ 45~59歳
❹ 60~64歳
あなたの離職時の年齢が何歳になるか下記計算式の番号にあてはめて、計算してみましょう!

計算式
❶ 0.8 × 賃金日額
❷ 0.8 × 賃金日額 – (0.3{(賃金日額 – 5,030) / 7,350} × 賃金日額
❸ 0.5 × 賃金日額
❹ 0.45 × 賃金日額
❺ 0.8 × 賃金日額 – (0.35{(賃金日額 – 5,030) / 6,090) ×賃金日額
❻ 0.05 × 賃金日額 + 4,448
基本手当日額の下限額は年齢に関係なく2,125円です。
また、離職年齢ごとの上限金額は以下のとおりです。

※2022年8月1日に更新された厚生労働省のデータを参考にしております。
基本手当の計算は手順が多く複雑そうに見えますね・・・
ですが、ひとつひとつ進めていけばおもったよりも簡単に計算できます!
ここまでで、所定給付日数や基本手当日額の求め方を勉強してきました!
では、例を用いて実際にどのくらいの額になるのか、実際に計算してみましょう!
Aさん
年齢:27歳
離職理由:自己都合
離職前雇用保険被保険者期間:通算1年6ヶ月
毎月の給与支給額:18万円
180,000円 × 6ヶ月 = 1,080,000円(離職前6ヶ月の給与総額)
1,080,000円 ÷ 180日 = 6,000円(賃金日額)
0.8 × 6,000 – (0.3{(6,000 – 5,030) / 7,350} × 6,000 = 4,563円(基本手当日額)
4,563円 × 90日(所定給付日数)= 410,670円
Bさん
年齢:40歳
離職理由:会社都合(特定受給資格者)
離職前雇用保険被保険者期間:通算10年2ヶ月
毎月の給与総額:40万円
400,000円 × 6ヶ月 = 2,400,000円(離職前6ヶ月の給与総額)
2,400,000円 ÷ 180日 =13,333円(賃金日額)
0.5 × 13,333円 =6,666円(基本手当日額)
6,666円 × 240日(所定給付日数)= 1,599,840円
AさんとBさんでそれぞれ離職理由・年齢・被保険者期間・離職前給与額が違うので、
賃金日額や給付日数に差が大きく生じ、もらえる金額が全然違いますね・・・!
みなさんも自分の状況にあわせて一度計算してみてください!
※上記はあくまでも計算例です。
給付額は大体わかったけど、どうやって申請して、どのくらいの期間で給付されるんだろうと思いますよね。
基本手当を申請するためには、必要な書類を揃えてハローワークで手続きをする必要があります。
申請から受給までのながれは、以下のとおりです。
会社から離職票が届いたら、自宅住所を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みを行ってください。
用意する書類
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
・マイナンバーカードまたは個人番号の記載のある住民票
・身元確認書類((A)のうち1種類、Aがない場合は(B)のうち異なる2種類(コピー不可))
(A)運転免許証、運転経歴証明書、官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(B)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証明書など
・写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2,4cm)
・本人名義の預金通帳かキャッシュカード
ハローワークが基本手当の受給要件を満たしているかを確認し、受給資格の決定ならびに離職理由の判定を行います。
受給資格が決定した後に受給説明会の日時が通知され、「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されます。
指定の日時に「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑や筆記用具を持参して出席します。
出席すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を配布され、第一回目の「失業認定日」が案内されます。
原則、4週間に1回、失業の認定がされます。指定日に管轄のハローワークに行って「失業認定申告書」に記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出してください。
基本手当を受けるためには、失業の認定機関の間に原則2回以上の求職活動が必要となります。
失業認定日から通常5営業日程度で、あなたが指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。
参考:雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス
基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間です。
この期間内かつ、受給手続きを行ったあとの失業状態にある日について、上記所定給付日数を上限として基本手当が受けられます。
そのため、この期限を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていてもその日以後は基本手当を受けることができなくなりますので、早めに手続を行いましょう!
いかがでしたか?
基本手当は退職や転職を考えている方にはとても心強い制度だということがわかりました!
ただし、受給要件や給付日数には注意する必要があります。
これを機に基本手当についてしっかりと学んでおき、退職後の金銭面の不安を少しでも解消できるように計画を立てておきましょう!
アシタバでは転職を考えていらっしゃるかたに寄り添ってお仕事探しのサポートをさせていただきます!
どうぞお気軽にお問合せください♪