
【2024年6月開始】1人あたり4万円の減税!定額減税の適用条件や減額方法を解説
BLOG

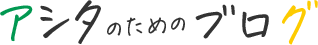
 その他
その他
社会人として毎日仕事をする中で、どうしてもストレスを感じてしまうことはありますよね。
仕事内容、職場環境、通勤時間、職場での人間関係などなど…
ストレスの感じ方は人によって違いますが、その中には様々な要因が隠れています。
ストレスの要因は何なのか、改善するためにはどうすれば良いのか、悩んでもなかなか答えは見つからないものです。
そこで今回は、職場におけるストレスケアについて、ストレスチェックの制度や目的を中心にご紹介していきます!

ストレスチェックとは、
会社が定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知するとともにその検査結果を集団的に分析する、従業員の健康を守るための取り組みです。
検査には、ストレスチェックシートといわれる紙媒体の質問票、または、Webなどによる電磁的な媒体による質問票のどちらかを使用します。

ストレスチェックを行う最大の目的は、
自身のストレス状態を適切に把握することで労働者自身による早期のセルフケアを実現するとともに、職場の環境改善につなげるなど、メンタルヘルス不調を未然に防止することです。
まずは労働者のみなさんに自分がどれくらい仕事が原因で強い悩みやストレスを抱えたりしているか、いち早く自分の心の状態を把握してもらうこと。
そして、事業所が労働者一人ひとりのメンタルヘルスの不調や労働状況を検査結果から分析することで、労働者にとってより働きやすい職場環境を作ること。
労働者と事業所の両者で把握することにより、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためだけでなく、ストレス要因そのものを低減するよう努めることができる、というわけですね。
労働者のメンタルヘルスケア3段階
〈一次予防〉
労働者が自分のストレス状態に気づき、カウンセリングの受診やセルフケアを行うことでメンタルヘルス不調を未然に防ぐ。
〈二次予防〉
メンタルヘルス不調のある労働者がうつ病や精神障害などを発症しないように、早期に高ストレス者をみつけ適切な措置を行う。
〈三次予防〉
メンタルヘルス不調により休職する労働者の職場復帰の支援。
労働者が常時50人以上の事業所は、1年以内ごとに1回、定期的に実施することが定められています。
その背景には、近年の精神障害による労働災害の増加や、仕事に関して悩みやストレスを感じる労働者が半数を超えている状況などがあります。
しかしながら、労働者にとってストレスチェックの受検は義務ではありません。
なぜなら、受検すること自体が大きな心理的ストレスになり得るからです。
前述の目的を踏まえると、繁忙期に実施しない、検査結果による不利益がないことを伝えるなど、ストレスチェックの実施が労働者の負担とならないように配慮し、対象者全員が受検することが望ましいですね。
また、事業所はストレスチェックの実施後、労働基準監督署に「心理的負担の程度を把握するための検査結果報告書(様式第6号の3)」という報告書を提出しなければなりません。
実施義務のある事業所がもし実施しなかった場合
ストレスチェックを実施せず、労働基準監督署への報告を怠った場合、労働安全衛生法第120条の5により、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
前述したとおり、対象の事業所は1年以内ごとに1回必ず実施する必要がありますが、実施時期は事業所が定めてよいことになっています。
ただし、ストレスチェックは集団的な分析を行うことから、少なくとも店舗や派遣先ごとなど、集計・分析の単位となる集団については同時期に行うことが望ましいです。
ストレスチェックの対象となるのは「常時使用する労働者すべて」です。
ただし、以下に該当する労働者は対象外としても差し支えありません。
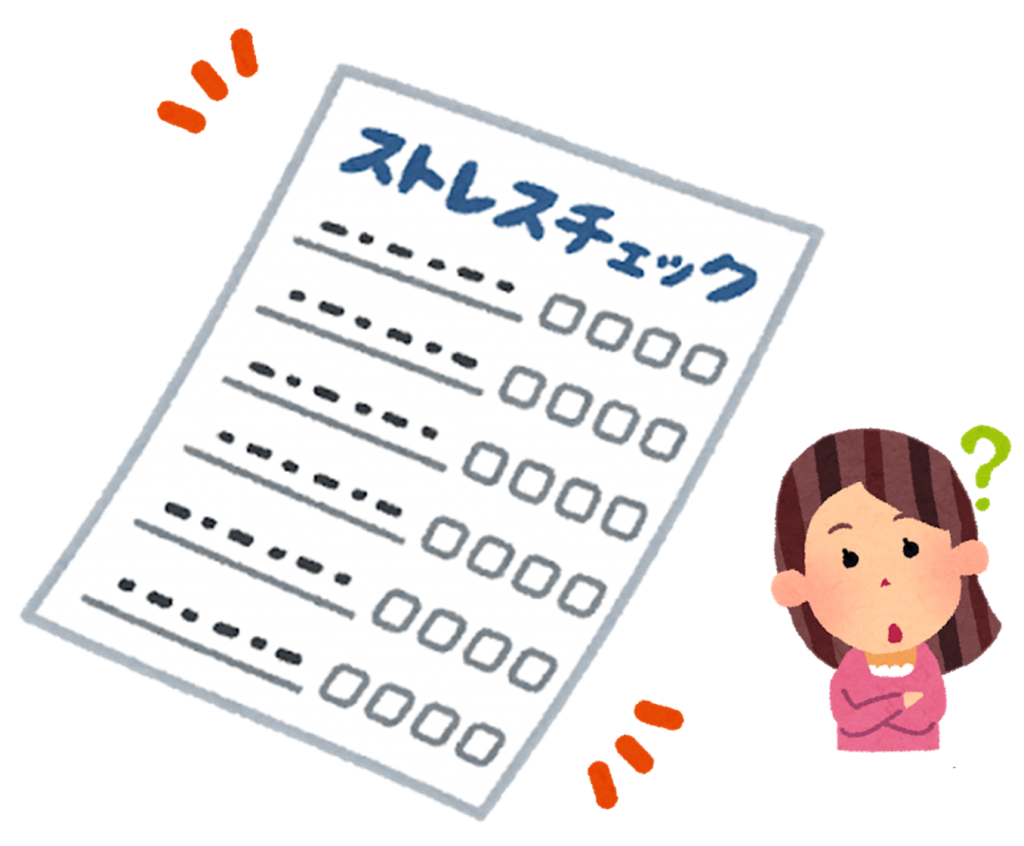
ストレスチェックは簡単な質問に対し、当てはまるものを4択から選んで回答します。
ストレスチェックは23項目、57項目、80項目、120項目と質問数に応じた種類があります。
最もベーシックなのはおおよそ5分ほどで答えられる57項目です。
アシタバでもこの57項目のストレスチェックを採用しています。
ストレスチェックは労働安全衛生法によって、以下3領域に関する質問を必ず含めるように定められています。
併せてどのような質問内容があるのかも一部ご紹介します。
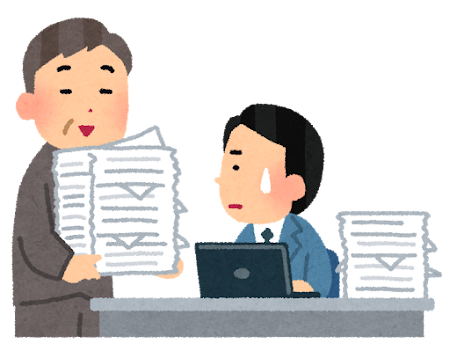
職場での心理的な負担の原因に関する質問
・非常にたくさんの仕事をしなければならない
・時間内に仕事が処理しきれない
・自分のペースで仕事ができる
・私の職場の雰囲気は友好的である

心理的な負担による心身の自覚症状に関する質問
・活気がわいてくる
・元気がいっぱいだ
・怒りを感じる
・物事に集中できない

職場における他の労働者からの支援に関する質問
・次の人たちはどれくらい気軽に話ができますか?
上司/職場の同僚/配偶者、家族、友人等
・あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?
上司/職場の同僚/配偶者、家族、友人等
厚生労働省のストレスチェックツールを活用しよう!
・自分は事業所の実施対象者に該当しない…
・事業所実施のストレスチェックはあるけど自分のタイミングでチェックしてみたい…
そんな方も実施できる「5分でできる職場のストレスセルフチェック」という57項目のストレスチェックツールを厚生労働省が無料で公開しています。
早期のストレス状態把握のため積極的に活用しましょう!
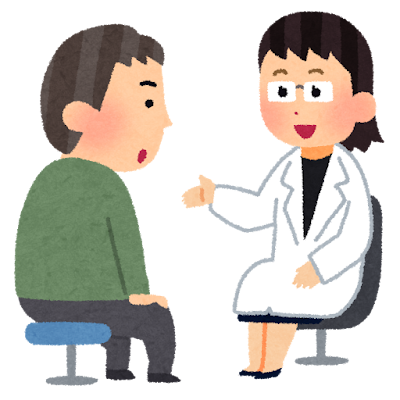
では実際にストレスチェックはどういう流れで行われるのでしょうか。
おおまかな流れは、以下のとおりです。

上記のとおり、ストレスチェックの回答から結果通知までは全員に対し行われますが、面接指導以降は本人が希望した場合のみ、集団分析は努力義務となっております。
したがって、ストレスチェックの結果が高ストレス者として面接指導の対象になった場合でも、希望しなければ医師の面接指導を受ける必要はありません。
面接指導がストレスになってしまっては本末転倒ですからね。

自覚があってもなくても溜まっていくのがストレスです。
趣味に没頭する時間をつくる、好きなものを食べる、運動をするなど自分なりのストレス発散方法をすでに見つけられている人は素晴らしいですね!
今回は仕事中にもできる簡単なストレス発散やリフレッシュ方法をいくつかご紹介します!
ストレスを感じたらぜひやってみてください!
ずっと同じ姿勢で働いていると身体に負担がたまりやすいので、意識的に伸びやストレッチをしたり、少し歩いてみたりしましょう!
少し身体を動かすだけでも血行が改善されたり、気分転換できますよ!
仕事中は頭を使うので、糖分を摂取して気分転換をしましょう!
特にチョコレートには疲労回復やリラックス効果など、ストレス軽減に効果があると言われています。
換気で窓を開けたタイミングなどで外の空気を吸ってリフレッシュしましょう!
外にランチを食べに行ったり、仮眠をとったり、スマホをみたり、一息つく時間はとても大切です。
決められた休憩時間にしっかりと休息することで、午後からも仕事を頑張れますね!
同僚や後輩など親しみやすい人が職場にいるなら、その人と会話をするのもリフレッシュに繋がるはず!
ストレスが多い時に、話を聴いてもらうだけでも気持ちは楽になります。
また、話をすることにより気持ちが整理されたり、良いアドバイスをもらえることもあります。
仕事の話はもちろん、趣味などの仕事以外の会話をして親睦を深めることもできますね!

ストレスチェック制度は、従業員の健康を守るための取り組みです。
自分自身が抱えるストレスに早く気付くことで、面談やカウンセリングなどのセルフケアにつながり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことができます。
また、企業にとっても職場環境の改善につながり、生産性アップや離職率低下といったメリットがありますね。
お勤めの事業所でストレスチェックの案内があった際は、ぜひご活用いただき、
ご自身のストレス度合いを確認してみてください。
もちろん、ストレスチェックだけではわからない職場や職場以外でのストレスを抱えている場合もあるはず。
そんなときは自分ひとりで抱え込まずに、周りの人に相談してみることもメンタルヘルスを保つために重要なことです。
もし周りの人に相談するのが難しい場合は、下記のような相談窓口も利用してみてください。
相談窓口:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
アシタバではストレスチェック実施のほかにも、担当スタッフによる定期的な面談やLINEでのお問い合わせなど、みなさんが働きやすい環境作りを目指しています。
もし、今の職場でストレスを抱えていて転職を考えていたり、お仕事のお悩みなどございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください!