-27-150x150.png)
働いている人は使わないと損?教育訓練給付金をわかりやすく解説します~教育訓練①~
BLOG

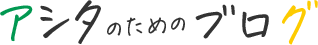
 その他
その他
暑い夏が札幌にもやってきました。
エアコン無しでは耐えられない暑さに加え、物価高で電気代も増加しています。
そこで、昼食代を節約するために多くの方が外食を控え、会社に「お弁当」を持参しているのではないでしょうか。
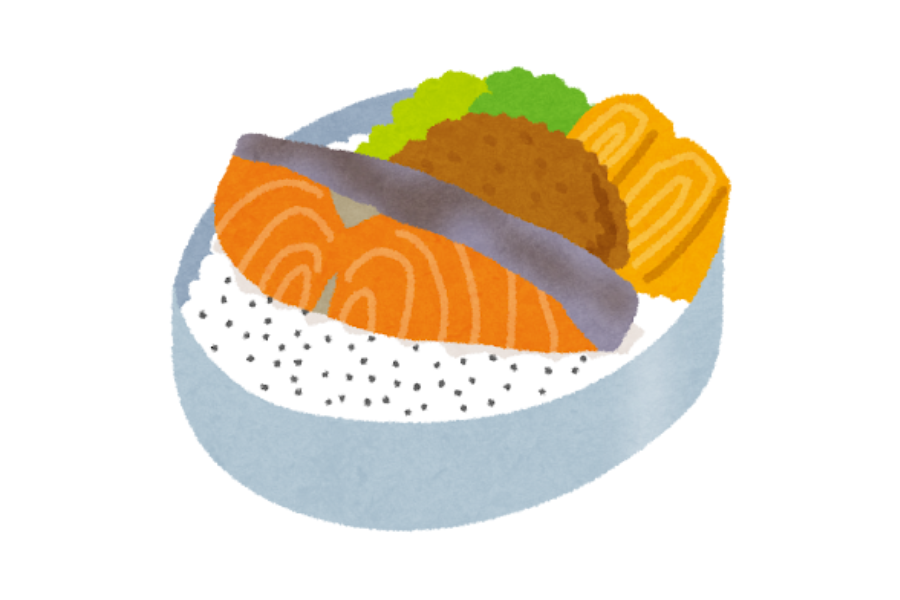
夏は食中毒警報が頻繁に発令されますが、「自分が食中毒になるわけない」と他人事に思っていませんか?
実は、家庭での食中毒の件数が最も多いのです!
特に7月〜9月の高温多湿の時期は要注意。
お弁当は調理から食べるまで時間が空くため、食中毒菌が繁殖しやすいです。
今回は夏のお弁当の注意点についてお伝えします。

食中毒の発生原因は3つに分類されます。
1.細菌性食中毒:食品に細菌が付着、繁殖
2.ウイルス性食中毒:ウイルスの付着による
3.自然毒食中毒:毒キノコやフグなどの自然毒
その中でも夏に多いのは細菌性食中毒。
細菌は35℃~40℃で最も増殖しやすいのです!!
それでは今回は<細菌性食中毒>の種類と、その発生原因・症状をご紹介します。
集団食中毒で度々ニュースになる食中毒菌もあるので、皆様も聞き覚えがあるのではないでしょうか。
重度になると死に至ることもあり、大変恐ろしいです。

食中毒から身を守る大事な3原則は…
1.細菌を食べ物に「つけない」
・調理前に手を洗う
・生肉や魚を切ったまな板や包丁で他の食材を切らない
2.細菌を「やっつける」
・食品を75℃で1分以上加熱する
3.細菌を「増やさない」
・水気の出やすいおかずを避ける
・おかずを冷ましてから詰める
・保冷剤や保冷バッグを活用し、冷蔵庫で保管する

お弁当で気を付けるべきことの具体例をご紹介します。

食中毒の原因は食べ物ばかりではありません。
水分補給のために持ち歩くペットボトル飲料にも危険が潜んでいます。
ペットボトルに口をつけると、口の中の細菌が入り込んで増殖し食中毒の原因となるそうです。

ペットボトルに入り込んだ細菌や微生物は25℃~30℃の環境で最も増殖しやすいため、夏場は特に注意が必要なのです。
特に以下の飲み物に注意⚠
乳製品のタンパク質、糖質、麦茶の炭水化物が細菌の栄養源となるとのことです。
車に置きっぱなしにしたあと、飲みかけを飲んだことありませんか?
決して他人事ではないですね。
夏にペットボトルの飲み物を持ち運ぶときは速やかに飲み切るか、ペットボトルカバーで保冷して温度が上がらないようにすることが大切です。
持参したお弁当で食中毒になってしまうと、仕事を休まなければならなくなり、病院の費用もかかります。
節約のためのお弁当が逆効果になってしまいますね。
この記事を参考に、美味しくコスパの良い昼食で健康に夏を過ごしていただけたら幸いです。

今の職場には冷蔵庫や電子レンジもないとお嘆きの方、利用可能な職場やご希望であれば社内食堂のある職場のご紹介も可能ですので、LINEでお気軽にご相談ください!
なお、アシタバ公式LINEでは、お仕事情報の配信だけではなく、「知らなかった!」となるような「お役立ち情報」を不定期ですが更新しています。
友達追加よろしくお願いします!